1995年の阪神淡路大震災は小松左京が愛する国で、大切な同胞が見舞われた恐るべき災難であり、また被害の中心が自分の生まれ育った阪神間で起きた災害であったため大きな衝撃を受けました。
小松左京は、震災から2カ月あまり経った1995年4月1日から、毎日新聞に週1回のペースで『大震災’95』の連載を始めました。
淡路島をはじめとして各地の被災現場をたずね、当時、戦後最大の災害であった阪神淡路大震災の生の記録をとどめようとしたのです。
2017年にリリースされた電子書籍「日本沈没 決定版」の解説より、阪神淡路大震災と小松左京に関するエピソードをご紹介します。
<電子書籍「日本沈没 決定版」>解説13~ 阪神淡路大震災への対応(小松実盛)より

『日本沈没』を発表後、二十年以上が経過した、一九九五年一月一七日早朝。当時としては、戦後最大の被害を出した、阪神淡路大震災が発生しました。
小松左京は、震災当日の模様を次のように書き残しています。
ヘリ空撮がはいって来た。それはアナウンサーの読む交通体系のダメージ情報どころではない衝撃を私にもたらした。神戸の長田区から、五ヵ所も六ヵ所も、天を暗くするほど茶色の煙が上り、下にまっ赤な炎がちらちら見える。…地震に火災はつきものというが、この火災の大きさと、火点の多さはどうなるんだ。これじゃ周辺に酸欠が起るし、消防車も近くへ行けないぞ!
十階だてぐらいのビルが、ぐしゃっとつぶれている。片脚が折れたように斜めにかたむいている。つんのめったり、のけぞったり、中にはもののみごとにうつぶせにひっくりかえり、道路をふさいだりしている。壁が生皮をはがれたように剥落し、茶色の下地が出ているビルがある。それがどうやら三宮から市役所前を通って税関の方へ行く神戸市目抜きの「フラワーロード」らしいとさとった時、手がふるえてきた。――ヘリは移動し、カメラがズームし、国道ぞいの倒壊家屋をうつし出す。へしゃげた折紙細工のようになった店舗の間に、茶色の木っ端の帯となった木造家屋の残骸がつらなる。鉄道がうつし出され、軌条脇に横ざまにたおれたべージュとオレシジ色の六輌編成の電車や、何編成もの電車の列が、操車場らしい所で、中央部が陥没するようにへたりこんでいる状景がうつる。たおれた電柱、落下したガード……。
「こりゃ、震度6どころじゃないぞ!」と私はかすれた声で妻にいった。「震度7-いやもっと上まわる所だってある……」
妻は眉をひそめて画面を凝視したまま返事をしなかった。
そして――「あの状景」がうつった時、私は腰がぬけた。実際は、急な脳貧血で、下半身に血が移行し、腰から下が岩のように重く感じられたのだが、その時は一瞬そう思った。視界が暗くなり、数秒間色覚がぬけた。それほど「何百メートルにもわたって横たおしになった阪神高速の高架」の映像がもたらしたショックは大きかった。貧血のため、眼球を動かすのさえ重い感じだったが、無理に眼をこらして、その映像をチェックした。根元からぐにゃりと折れ曲った何十本もの橋脚、北側にたおれ、ほとんど垂直にちかい斜めの壁のようになって、下を走る国道四三号線の上り線の上にそびえたっている道路面……思ったより下におちている車の数はすくないな、と、私は膜のかかったような頭の隅で考えていた。――火災もあまり発生していないようだ。朝早く地震が起って、交通量が少なかったのだろう。
「阪神大震災の日 わが覚書」より
小松左京は、『日本沈没』の中で、高速道路が倒れるシーンを書いたところ、耐震工学の権威という方から、人を介してで「高速道路が倒れるはずがない」と非難されたと語っていました。
高速道路をすっとばしていた車は、まず、いくつもの地下道の合流点で、ハンドルをとりそこなって柱にぶつかるもの、追越し途中で接触するものがあいついだ。地下道はたちまち火と黒煙の吹きぬける煙突となり、急ブレーキをかけるとすぐそのあとから、後続車が七、八十キロのスピードでつっこむ、といった玉突き事故が起こった。
高架の上でも同じことだった。ハンドルを切りそこなって、低い中央分離帯をとびこえ、対向車と正面衝突するもの、カーブで、側壁へぶつかるもの、ジェットコースターのコースのように、急カーブと上下の坂が組みあわさっている西神田[にしかんだ]付近では、上下動の初期に空中へ飛び上がった車さえあった。--そして、河川を埋めたてた上につくった部分の数カ所で、高架道路の橋脚はもろくも傾き、道路はひん曲がって、何百台もの自動車を、砂をこぼすように地上にぶちまけた。--洩れたガソリンの上に、団子衝突の火花がとび、たちまち引火する。東京の空からは、火と車の雨が降ったのである。
『日本沈没』より
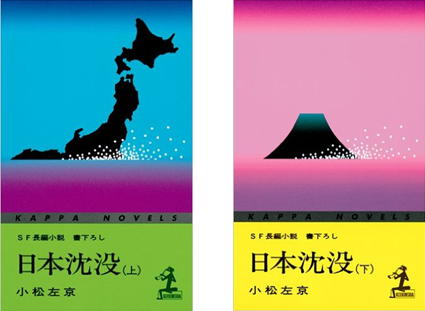
実は、阪神淡路大震災が起きた朝、この解説を書いている私自身も、仕事の関係で、自宅のある神戸から大阪へタクシーで移動していました。
午前五時四十六分、地震が起きたその瞬間、激しい揺れとともに阪神高速道路上を走っていたタクシーが蛇行してゆきました。
照明塔がメトロノームのようにゆっくりと左右に振れ、道路そのものがまるで水面のように波うちます。そして、グーン、グーンと巨大な金属がきしむ音が響き続けます。
追い越し車線を走っていたトラックが、道路が傾いた時に、吸い寄せられるようにこちらの方に近づき、鏡のようなタイヤホイールに、一瞬自分の顔が映ったのを鮮明に覚えています。
危機な状況でしたが、周辺で玉突き事故や、側壁にぶつかる車両もありませんでした。
まだ、陽ものぼらぬ早朝。高速道路を走るのは、トラックやタクシー、あるいは様々な業務用車両と、運転のベテランがほとんどで、また車両そのものが少なかったのも幸いしたようです。
地震発生直後、スピードを落とし側道に停車しようとする車が皆無だったので、その件を、地震後随分経ってから当のタクシーの運転手さんに尋ねたところ、「あの激しい揺れの中、スピードを落としたら、ハンドル操作ができず、側面に突っ込む可能性もありましたよ。あえて、アクセルを踏み込み、パワーを与えることで、車をコントロールできたのです」と教えてくれました。プロの的確な対応で命拾いしたわけです。
しかし、自分が通過した地点より後ろの阪神高速道路は、六三五mに渡って倒壊し、これに伴い一六人の方が亡くなられています。ほんの数分遅れていたら、自分も命を落としたかもしれない。亡くなられた方のご冥福を心から祈らずにおられません。
神戸を含めた、阪神間を中心に、大きな被害を出した、阪神淡路大震災が発生した、その当日から、『日本沈没』の作者である小松左京に、スポーツ新聞からの問い合わせを皮切りに取材が殺到します。
いずれにしても、これが一週間に二十数回という、活字、電波マスコミの「取材攻勢」の皮切りだった。――スポニチからの電話を切って、十五分もたたないうちにまたかかって来た。今度は共同通信の東京だった。つづいて、東京新聞、いずれも、十五分から二十分の間隔をおき、一回の電話インタビューが、三十分から四十分、それもできるだけ内容が重複しないように、視点をかえたコメントをひねり出すので、頭の中がくたくたになってきた。妻に、書斎に握り飯と茶をはこんでもらい、私は電話の横に居つづけた。電話の間、古い地震関係のファイルや、百科事典、地学関係のテキスト、理化学事典などをひっぱり出して、知識の復習をした。何しろ電話でコメントを求めてくる記者は、すべてまっ先に「日本沈没」の事をいった。たしかに、ベストセラーにはなったが、二十二年も前の作品を、読んでくれている現役記者が、そんなに多いとも思えなかったが、あとで聞いてみると、若い記者は映画やビデオテープで見たり、中には、さいとうたかおさんの「漫画」でよんだ、という人もいて、「時代」というものを考えさせられた。――ダイジェスト版だが、英語をはじめ十一ヵ国語に翻訳されていたためか、あとから「ウォールストリート・ジャーナル」や「ニューズウィーク国際版」「シュピーゲル」「ル・モンド」「レプブリカ」などの編集部、記者のインタビューもあった。
<中略>
――長い長い一日だったが、しかしそれで終ったわけではなかった。その夜、私はまっ赤に燃え上る業火に包まれてうろうろする夢を見た。同じ夢を三日間たてつづけに見て、三日目にやっと、それが五十年前、昭和二十年の八月はじめに経験した、阪神間の夜間大空襲の夢だとわかったのである。
「阪神大震災の日 わが覚書」より
『日本沈没』の執筆の動機となり、生涯付き纏いつづけた、小松左京の心の底にある戦争の深い闇が、目の前で起きた大地震をきっかけに再び広がり始めていました。
戦争の悲惨さを思い起させる大地震の被害の数々、係われば過去の記憶が連鎖的に呼び起こされ、さらに苦しむことになることは十分予想できたでしょう。
しかし、小松左京は、あえてその道を選ぶことになります。あの物語を書いた責任を取るかのように。
震災発生から七五日後にあたる、四月一日より、毎日新聞で一年間にわたって展開する予定だった宇宙をテーマにした連載を急遽差し替え、被災地での取材と地震に関係する各界の権威と対談する、月一回の連載「大震災’95」をスタートさせました。奇しくも、戦争末期に自らが阪神間にある西宮の自宅で空襲を経験してから、ちょうど五十年が経っていました。
あの日から七十五日
きょう一九九五年四月一日は、あの「阪神・淡路大震災」が襲った一月十七日から、ちょうど七十五日目にあたる。
七十五日といえば、つい、人のうわさも……という言葉が思い浮かぶ。もとよりこれは、無責任な者のうわさについての俚言[りげん]であるが、しかし、その背景には、地震、台風、洪水、大火など、災害の多い風土の中で育った一つの精神文化として、すべてはうつろい行くという無常観と、恢復力[かいふくりよく]の強い自然の中で、いつまでもくよくよ嘆いていてもはじまらない、という諦念をこえる指向の伝統と、通底する所があるようにも感じられる。
だが、私は逆に、この大震災発生以後二カ月余あたりから、この「巨大な災害」が、私たちの社会と生活にもたらしたショックと影響の「全貌」をとらえる作業にとりかかるべきだと思う。 --なぜなら、あの時不意に、阪神間の足もとから牙をむいて襲いかかってきた、私たちにとっても、社会にとっても、まったく「未知の体験」だったあの大災厄のもたらした、衝撃と、どこまで広がるかわからなかった多元的な混乱も、このあたりでやっと鎮静化にむかい、それにつれて、この災厄の複雑な「全貌」と性格も、ようやくぼんやりと把握できるようになってきたからである。
だが一方、六千人を超える死者と、数万人の負傷者、十数万戸の全半壊、焼失家屋、数十万人の被災者を瞬時に現出した、この地域のはげしい痛みと疼[うず]きは、ようやく薄皮のはり出した社会の表面の下に、まだ熱をもって残っている。 --こんな所に、行政効率だけを優先させた軽々しい「復興計画」を、「お上」の方からつきつけたら、厳しい反発がおこるのは当然だ(地域行政末端の不慣れもあったかも知れないが、ようやく生死の境を脱したが、なお病床に呻吟[しんぎん]する患者にいきなりペンをつきつけ、遺産を公共に寄付する、という遺言に今すぐサインしろ、と迫るような無神経さを感じさせる)。
いずれにしても、近隣周辺を含めて、この災厄に対する「記憶の痛みと疼き」の生々しいうちに、「総合的な記録」の試みをスタートさせなければならない、と思う。
『大震災’95』より

この連載を開始した時、小松左京は六四歳、物語の中の田所博士とちょうど同じ年になっていました。
震源にもっとも近い淡路島をはじめ、各地の被災現場をたずね、地震学者、ガス・電気・水道といったインフラ、自衛隊、消防、マスコミ、さらに精神科医といった様々な方面を取材し、連載第一回で読者に呼びかけたように、この当時、戦後最大の災害であった阪神淡路大震災の生の記録を自らの手で残そうとしました。
しかし、還暦をすぎた老いた身体に鞭打っての震災取材は、自身の思い入れが強かったが故に、心身ともに大きな負担となりました。
この取材を通じて、傷ついた被災地を目の当たりにするにつけ、そして天災だけでなく、人災が被害を広げた事実を知るにつけ、この悲惨な現実が、自らの過去の巨大なトラウマである、戦争と終戦直後の混乱の記憶を、さらに呼び起こすことになりました。
震災の夜から始まった、小松左京の心の底に巣くっていた戦争の闇は、一年あまりの連載で、よりいっそう広まってしまったのです。
小松左京は、生涯で一七の長編、二六九の中短編、一九九のショートショートを書いたとされています。
未発表のもの、また漫画や舞台の台本を含めれば、生み出した物語の数はさらに多くなるでしょう。
しかし、この震災以降、小松左京は一本たりとも、自らの手で物語を生み出していません。
日本沈没 第二部』を書くことは諦めていました。しかしライフワークでもある、宇宙と人類の関係をテーマにした『虚無回廊』は、何とか完成させたいと願い、気力が少し回復してから準備を進めるのですが、結局、それが実現することはありませんでした。






-300x200.jpg)



-300x225.jpg)

